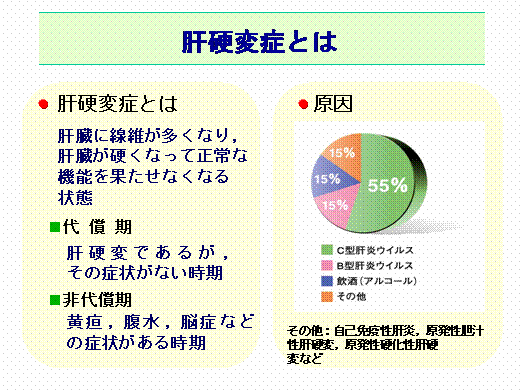がん発症のメカニズム、白血球の自律神経支配で明らかに
~世界的免疫学者が解き明かす疾病予防・治癒に至る道
2月11日(水)、科学技術館サイエンスホール(東京都千代田区)でシンポジウム「自然治癒力の時代へ」が開催された。この中で、「免疫革命」の著者としても知られる新潟大学大学院医歯学総合研究科教授の安保徹氏が「自然治癒力はすべて生き方にかかっている」と題して講演を行った。
副交感神経を優位にして免疫力を高める
人はいかにして、病気になるのか---。
「何か遺伝子に異常があってということではなく、あまりに無理な適応を超えた生き方をしたため、破綻をきたし、病気になったのではないか」
冒頭、安保氏は疾病の成り立ちについてそう指摘した。「無理な生き方からくるストレス」が、疾病発症の大きな誘因になっているという。そのため、がんをはじめとするさまざまな疾病に罹患している人々はまず「生き方を見直すべき」と安保氏はいう。それが免疫の仕組みによる疾病予防・治癒に至る道であると説く。
さまざまな疾病の中で、現代医学の粋を結集しても未だ死亡率の上昇が止まらない、がん。がんへの対処について、がんと診断された際に実施すべき4ケ条を安保氏は次のように挙げる。
1)生活パターンを見直す
2)がんの恐怖から逃れる
3)消耗する治療は受けない、続けない
4)副交感神経を優位にして免疫力を高める
この4ケ条は、「がん罹患後」のみならず、免疫学的な観点からの「がん予防」のための心得ともいえる。
このうち3つは、心の領域に関わるものである。「ストレス」を緩和し、副交感神経優位型に心身をコントロールする。そうした、心安らかな状態においては免疫力が高まり、さまざまな疾病を遠ざけ、健康な身体を維持することができるという。
人は生きていくうえで、とかく交感神経優位型になりやすい。しかしながら、「私たちはいろんな組織障害の病気を起こす。そのナゾは実は交感神経緊張状態にあった。その極限にがんがある」と安保氏は指摘する。
安保理論とはいかなるものか---。
その前に、我々の身体調節を司る「自律神経」についてよく理解しておく必要がある。
外部から浸入するさまざまな細菌やウイルスを駆逐する白血球が、「自律神経の支配下にある」というのが安保理論の骨格となっているからだ。
交感神経優位で顆粒球、副交感神経優位でリンパ球増やし防衛体制整える
自律神経は交感神経と副交感神経との拮抗により調節されている。1日のうちで、活発に動いたり、興奮したりする昼間は交感神経が優位に働き、ゆったりとリラックスする夕方から夜は副交感神経が優位に働く。季節でいうと、冬は交感神経が、夏が副交感神経が優位に働く。
我々を細菌やウイルスから守る白血球は、こうした「自律神経の支配下」にあると安保氏は説く。以下、概要は次のようなことだ。
白血球は、基本細胞であるマクロファージ、マクロファージから生まれた貪食能の強い顆粒球、免疫を高めるリンパ球の3種類がある。血液中においては、それらが、5:60:35の比率で存在する。
顆粒球はさまざまな分解酵素を持ち、大量の活性酸素で体内に侵入した異物を処理する。また新陳代謝も高める。しかし、顆粒球は増え過ぎると、常在菌をさらに攻撃し、化膿性の炎症を発現させるようになる。顆粒球は短期間で死滅するが、その際に活性酸素を出し、周囲の組織を酸化・破壊させる。
リンパ球は、細菌が浸入した際に、すぐに臨戦体制をとる顆粒球と違い、ふだんは休んでいて、マクロファージからのサイトカインという物質の情報により、抗原の侵入に気づいてはじめて活発な分裂を繰り返し準備態勢を整える。
マクロファージは、リンパ球に指令を与え、後にリンパ球と抗原との戦いの処理を行うという重要な役割を担う。
こうした白血球は自律神経の支配下にあり、交感神経が優位になると顆粒球が増え、副交感神経が優位に働くとリンパ球が増えるというメカニズムで我々の身体を効率良く守る。
白血球の自律神経支配の法則を8年ほど前に発見
生物の進化の過程で、白血球は自律神経の支配下に入り、顆粒球が交感神経に、リンパ球が副交感神経にと、それぞれの役割を分担し、防御効率をより高めるようになっていった。このことを安保氏らは8年ほど前に発見する。
「顆粒球は交感神経支配に入りましたが、私達生物が興奮するのはどういう時か。仕事、スポーツ、悩むとか、いろんなことがありますが、基本的に野生生物が興奮するのは、空腹が続いてエサを取るという行動を起こす時です。この野生の感覚は私達人間にもまだ残っていて、生きていくうえですごく大切ですが、エサ取りの行動を起こす時というのは生物の手足が傷付いて細菌が侵入してきます。そのため化膿性の炎症を起こして治癒するという細菌処理に優れた顆粒球を増やしておく必要があったわけです」
顆粒球は防衛機能の6割を占め、細菌の侵入を炎症という形で処理する。こうした防衛系においては、リンパ球による免疫機能は介在していない。
リンパ球はというと、「私達は今でも小腸の周りを中心に厚いリンパ球の層でおおわれています。免疫は基本的には、食べ物と一緒に入ってくる小さな異物、ウイルスとか花粉、ダニの死骸、ほこりとかを効率よく処理するために消化管とともに働きます。消化管は副交感神経支配ですから、リンパ球も消化管とともに副交感神経の支配下に入りました」
顆粒球とリンパ球のアンバランスは特有の疾病招く
ところで、こうした顆粒球とリンパ球の防衛機能は60:35というバランスを保っている間はいいが、どちらかが過剰になると特有の疾病を誘発するようになる。
イライラや悩みといった精神不安を抱え、交感神経の緊張状態が続くと、顆粒球の増加を招く。
「顆粒球は骨髄で作られ、血中に出て常在菌の存在する粘膜で一生を終えますが、これが多くなると顆粒球の放出する活性酸素で粘膜が破壊される病気になります。具体的には、歯槽膿漏とか痔とか胃潰瘍とか潰瘍性大腸炎で、顆粒球の炎症です。胃がやられる時も悩みを抱えた時です」
一方、副交感神経が過剰に優位になるとどうなるか。「リンパ球過剰の病気になります。典型的なのはアレルギー疾患です。今、日本の子供達はアトピー性皮膚炎とか気管支喘息とか通年性鼻アレルギーになる子供が増えています。楽をして大事に育てられた子供達はリンパ球が過剰になっていて、ちょっとした常在する抗原に反応してアレルギーを発症してしまいます」
交感神経優位では顆粒球が増え、副交感神経優位ではリンパ球が増える。どちらもそれぞれ特有の疾患を誘発する。
「健康な人は顆粒球とリンパ球が6:4くらいの比率です。もっと正確にいうと私達のリンパ球の正常値は35~41%です。この範囲に入っていると健康で、免疫力十分な世界です。ですが、リンパ球が35%を割ると顔色がすぐれない、30%を割ると早期のがんとか組織障害の病気に入ります。20%近くになると進行がんの世界に入ります。逆にリンパ球が45%を超えるとじんましんが出るとか、身体がかゆいとか過敏反応が出てきます。40%を超えると確実にアレルギーの世界に入ります」
顆粒球とリンパ球の防衛機能は絶妙なメカニズムで成立しているが、ヒトはこうした自らを癒すプログラムを進化の過程で獲得した。顆粒球とリンパ球による修復機能は、いわゆる「自然治癒力」と呼ぶに値するものであろう。
しかしながら、こうしたヒトが本来備えている「自然治癒力」を抑制させるようなことが現代医療の世界でおきている。
一体、どのようなことか---。
不快な反応は治癒へ至る道、無理に抑え込まない
現代人は熱や痛み、かゆみ、下痢とさまざまな不快な症状が出ると、どうしても薬に頼ることになる。誰しも、早くそうした症状から逃れたい。患者の苦痛を一刻も早く取り除きたいとの思いから薬剤が研究・開発されてきた。しかしながら、免疫学的な観点からいうと、決して好ましい対処法ではないという。不快な症状の発現は副交感神経の修復に向かう反射で、免疫機能の発動であり、治癒に至る道であると安保氏はいう。
悩みや苦しみといった日々のストレスが続き、交感神経の緊張状態が続くと、顆粒球が過剰に増え、さまざまな病気を呼び込むようになる。「顆粒球増多による病気は、病気のほとんどを占めるほどありふれた病気です。歯槽膿漏、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵炎、クローン病、潰瘍性大腸炎、痔、こうした病気が無理したり、苦悩したりして起こります。
私達は正常な健康な組織が無理して壊された時に、必ずエネルギー代謝を高めて修復しようとします。その修復反射が実は副交感神経反射でした。治るための反射です。こういう副交感神経反射を目一杯使って血流を増やし、代謝を上げて組織を修復します。 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
痛みを作る。熱を持つ。血流を回復する。下痢をする。こういう反応はプロスタグランディンの作用が中心です。プロスタグランディンは発熱物質であり、痛み物質であり、炎症物質ですから、私達にとっては不快です。ですが、組織を修復するためにこの過程は必要なのです。
例えば私達は霜焼けになっても治る前に腫れ上がって治ります。太陽に当たりすぎても、火傷をしても腫れあがって治ります。組織が破壊された時は、必ずこうした修復過程を経て治ります。こういう概念がないと、熱が出たり、痛んだりすると大変ということで、止めにかかります。そして消炎鎮痛剤とかステロイドを使います。こうしたものはみな血流を止めます。血流を止め、組織反応を起こせなくすると、炎症反応は止まります。ですがこれは治ることと逆行することです。不快な反応は治癒反応であるということを私達は理解すべきです」
事故による負傷や急性疾患、あるいは感染症といった緊急の対応に薬剤が有効性を発揮することは誰もが認めるところではある。近年抗生物質が感染症に果たした役割は大きく、国民の健康管理にどれほど貢献してきたか計り知れない。しかしながら、一方で、対処療法的に薬を長期使用することで、逆に疾病を慢性・難治化している状況も生じている。
がんはいかに発症するのか
では、がんはどのようなメカニズムで発症するのか----。
交感神経優位で顆粒球が増え、副交感神経優位でリンパ球が増える。どちらかが過剰に増えると、それぞれ特有の疾患を誘発する。疾病のほとんどが、交感神経優位の顆粒球過剰から引き起こされる。がんも例外ではない。
「早期胃がんも進行胃がんも進行大腸がんも激しい顆粒球増多によるものです。がんと診断される1、2年前何か大変じゃなかったですかと聞くと、みんな激しいストレスを抱えています。嫌々つらい仕事を長時間やる、それから悩み、また消炎鎮痛剤を長期に飲むというようなことが関わっています」
がん発症の背景には、免疫力を徹底して抑えるようなストレスがあり、交感神経の緊張状態が続き、顆粒球が過剰になるような状況があるという。
身体の中でがんが発生しやすいのは、細胞の再生・分裂が頻繁に行われる場所で、顆粒球の放出する活性酸素により増殖遺伝子が損傷し、発がんへと向かうという。
「がん遺伝子がはじめからあるわけではなく、正常な細胞が増殖に使っている増殖関連遺伝子が調節障害を起こしたのががん遺伝子」という。
毎日100万個のがん細胞が生まれているが、とりわけ生命力が強いというわけではなく、リンパ球で抑えられているという。
がん患者のほとんどはリンパ球が30%以下の免疫抑制状態にあり、リンパ球が30%を超えるとがんの自然退縮がはじまると安保氏はいう。
がんにどのように対処すればいいのか
具体的にがんにどう対処すればいいのか。
がんと診断された場合、前述の4ケ条を実行することを安保氏は薦める。これは、「がん予防」のための4ケ条でもある。
「がんとわかったらまず生き方自体を変える。これをやらないで内視鏡で早期胃がんが取れたとか部分切除でがんが取れたとかといってもまた今までと同じような生き方をしては再発します」
また、がんへの恐怖心がリンパ球を下げ、免疫力を低下させるという。
「2番目は、がんの恐怖から逃れることです。抗がん剤や放射線を使うと患者さんはすごく消耗します。がんの恐怖感から発がんしたときよりももっとリンパ球が減るということが私達の研究でわかっています。いくら発がんするといっても25%くらいのリンパ球の比率は保って発がんしています。脅かされて絶望になった人はリンパ球の割合が20%割ります。これはがんが暴れ出す極限までいっているということです」
また、抗がん剤治療の問題点も指摘している。
「3番目は消耗する治療は受けないことです。あるいは延々と続けないことです。食べることができるとか歩けるとかそういう基本的な体力がないことにはがんには勝てません」
さらに、免疫力を司る副交感神経を優位に保つ生活習慣を身につけることが大切という。
「4番目は積極的に副交感神経を優位にして免疫力を高めることです。私達の免疫系というのは副交感神経支配で循環器系や消化器系とつながっています。ですから、血行がいい、便秘がない、腐敗臭がないという状態にもっていかなければいけない」
軽い運動や笑うこと、また入浴は副交感神経を刺激し、免疫強化に役立つという。
真の治癒を得るために生じる反応
こうした4ケ条を実践していく途上で、がんの自然退縮がはじまるというが、留意すべきことがある。
副交感神経が優位になると、プロスタグランジン、アセチルコリン、ヒスタミン、セロトニンといった発熱や痛みに関連する物質が放出されるようになるため、1週間ほど熱や痛み症状(傍腫瘍症候群)が生じ、その後、リンパ球が増え、がんが退縮をおこすようになるという。こうした段階で熱や痛みの不快症状を鎮痛剤や消炎剤、解熱剤、ステロイド剤などで抑えようとすると、治癒反応を止めることになり、真の治癒から遠ざかるという。
「4ケ条を実践していくと、次第にリンパ球が上がっていき、22%だった人が、28%とか30%に近づくと患者さんの半分近くが微熱が出たり、高熱が出たりし始めます。この現象は昔から知られていて傍腫瘍症候群といいます。これは免疫抑制から逃れ、発熱してリンパ球の上昇が起こる反応です。あまり抗がん剤とか放射線をやっていると、リンパ球が上がらなくなります。こうした反応については今の現代医学には出てきませんが、昭和40年代頃はこうした発熱現象でがんは自然退縮するという論文がたくさん出ていました」
この傍腫瘍症候群については、現代医療の世界では、50年ほど前から抗がん剤の使用とともにいわれなくなったという。抗がん剤の使用により免疫が抑え込まれ、傍腫瘍症候群も出なくなってしまったためだ。
「抗がん剤と一緒に治験をやると、抗がん剤の免疫抑制に負けてしまい、中々リンパ球が上がってきません。しかし、リンパ球を減らす治療をしないでやれば今でも発熱して、傍腫瘍症候群が出ます」
薬剤偏重の現代医学の中で、精神領域がもたらす免疫作用は非科学的と放逐され、埋没していったのか。
安保氏は言う。「自分の持てる免疫の力でも十分傍腫瘍症候群が起きるわけですから、やはり4ケ条を実践して自分の力で発熱を起こすくらいの気持ちが大切です。風邪を引いてもウイルスと戦うためにリンパ球が増え、必ず発熱を伴います。発熱は副交感神経の極限で起こりますから、必ずだるくなり、横になりたいという体調になります。こういう現象を理解して風邪でも解熱剤は使わない。がんでリンパ球が増えて発熱したなら、解熱剤は使わないでがんを自然退縮に持っていくべきだと思う」
ヒトの持つ深遠な自然治癒プログラム
「ストレス」を緩和し、副交感神経優位型に心身をコントロールする。心の平穏な状態はリンパ球が活発化し、免疫力が発動し、さまざまな疾病が治癒へと向かう。
プラセボ(偽薬)による暗示にしろ、宗教にしろ、心をポジティブにすることで、身体機能にプラス効果がもたらされ、実際に疾病が癒されるといった症例はこれまでも多く報告されている。
そうした深遠な自然治癒プログラムが人間の身体に内在しているにもかかわらず、その発動を抑えていたのは、精神領域の作用を軽視した、現代西洋医学の処方に他ならなかったというのは言い過ぎであろうか。
精神領域からのアプローチを重視する、いわゆる代替医療と称されるさまざまな療法は、総じて副交感神経を優位にし、リンパ球の活性化を促し、自己治癒力を発動させるものではなかったか。
代替医療で、患者が快方に向かう症例がどれほど報告されようとも、治癒に至るエビデンス(根拠)が希薄である、未解明な領域であるとされ、正当派西洋医療からとかく一蹴されてきた。
なぜそうしたものが、疾病を快方へと向かわせるか、安保理論は免疫学的なアプローチから明確に解き明かしている。
安保 徹(あぼ とおる)
<略歴>
昭和22年10月9日生まれ。東北大学医学部卒。昭和47年に青森県立中央病院に内科研修、昭和49年に東北大学歯学部微生物学の助手となる。昭和54年に米国アラバマ大学に5年間留学。平成3年、新潟大学医学部の教授となる。現在、新潟大学大学院 免疫学・医動物学分野 教授。
<業績>
1980年:ヒトNK細胞抗原CD57に対するモノクローナル抗体(Leu-7)の作製
1990年:胸腺外分化T細胞の発見
1996年:白血球の自律神経支配の発見
2000年:マラリア感染の防御は胸腺外分化丁細胞によって行われる